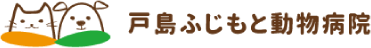腫瘍
寿命の延びと共に腫瘍も増えています

近年、ペットの寿命が延びたことで、悪性腫瘍(がん)が見つかるケースが増えてきています。
がんが発見される一番多いケースは、飼い主様が普段のスキンシップで体表にできたしこりに気づき、相談に来られることです。
日頃からペットの体に触れ、異常がないか確認することがとても大切です。
ただし、飼い主様が見つけやすい体表の腫瘍だけでなく、血液検査やレントゲン検査、エコー検査を行わないとわからない内臓の腫瘍も多くあります。がんが進行して症状が出る前に発見し、早期に治療を行えば、ペットの命や健康を守ることができます。
そのため、しこりに気を付けるだけでなく、ペットがある程度の年齢になったら、年に1回以上の定期的な健康診断を受けて、がんの早期発見・早期治療を心がけましょう。
犬・猫のよくある腫瘍
犬の腫瘍
・リンパ腫
・乳腺腫瘍(乳がん)
・口腔内腫瘍
・鼻腔内腫瘍
・皮膚腫瘍など
猫の腫瘍
・リンパ腫
・乳腺腫瘍(乳がん)
・口腔内腫瘍
・腸管腫瘍など
腫瘍の外科手術

がんの外科手術では、がんそのものやがんの疑いがある部分を外科的に摘出します。
がんの種類や状態によっては、手術によって完治を目指せる場合もあります。
手術は全身麻酔下で行われ、事前に検査と診断を行い、麻酔のリスクを慎重に確認したうえで実施します。
腫瘍が見つかった飼い主様へ
健康診断や検査の結果、もしがんが見つかった場合、手術で治療できるならばそれをおすすめします。
しかし、がんには治療が難しいものや、治療しても予後が悪いものもあります。
そうした場合は、がんの状態や治療の可能性を正直にお伝えし、飼い主様と一緒にペットのために何ができるかを考えていきます。
抗がん剤治療で延命が期待できる場合でも、副作用が出るリスクがあります。
延命を優先するのか、痛みを軽減することを優先するのかは、飼い主様の考え方次第です。
どの選択肢を選ぶかは様々ですが、当院では飼い主様の考えを尊重し、「がんだから終わり」というのではなく、「まだできることがある」という気持ちで、ペットと飼い主様に寄り添い続けます。
ヘルニア手術
犬や猫の椎間板ヘルニアについて

犬や猫の椎間板は、背骨と背骨の間でクッションの役割を果たしています。この椎間板が変性して軟骨の一部が飛び出し、近くの神経を圧迫すると、足や腰に強い痛みやしびれが生じることがあります。
症状が進行すると、歩行が困難になったり、排泄がうまくできなくなることもあります。
特に、腰部の椎間板ヘルニアは「家庭内の交通事故」とも呼ばれ、非常に危険です。
脊髄神経が圧迫されるため、人間でいう交通事故による脊髄損傷に近い症状が出ることがあり、下半身に麻痺が現れることもあります。
症状が重い場合や急速に進行している場合は、緊急手術が必要になることもあります。
首の椎間板ヘルニアも同様に、緊急手術を必要とするケースが多く、注意が必要です。
こんな症状はありませんか?
- 触られるのを突然嫌がる、触れると痛がる
- 歩き方が変わり、ふらつく
- 失禁や排便が困難になるなど
- ソファや階段などの段差を避けるようになる
- 自力で立ち上がれない
椎間板ヘルニアにかかりやすい犬種
椎間板ヘルニアは、特にダックスフントやコーギー、ビーグルなど、胴が長く足が短い犬種に多く見られます。
特にダックスフントは、先天的な軟骨形成異常があるため、若い頃から椎間板ヘルニアになりやすい犬種です。また、大型犬は体重による負担がかかりやすく、椎間板ヘルニアにかかるリスクが高いです。
椎間板ヘルニアの検査や診断
神経学的検査
神経反射や姿勢の検査を通じて、麻痺の有無や程度を調べ、脊髄のどこに問題があるのかを推測します。
レントゲン検査
椎間板ヘルニア自体はレントゲンでの診断が難しいことが多いですが、他の疾患がないか、背骨が曲がっていないか、椎間板が石灰化していないかなどの確認を行います。
脊髄造影・造影検査
脊髄造影は、椎間板ヘルニアの部位を特定するための特殊なX線検査です。
腰の骨の間に針を刺し、脊髄の周りに造影剤を注入して圧迫されている部分を確認します。この検査は診断精度が高く、95% の確率で椎間板ヘルニアを確定診断できます。
CT・MRI 検査
CTやMRI検査は、ヘルニアの部位だけでなく、脊髄損傷の程度や他の疾患を特定するのに非常に有効です。特に MRI 検査では、重度の椎間板ヘルニアが原因となる脊髄軟化症の診断が可能です。
骨折などの整形外科手術
骨折について

犬や猫の体は、骨格が支えることで体重を支え、運動を可能にしています。しかし、この骨に強い力が加わると、骨折が起こります。
骨折は、どの骨がどのように折れているかによって様々なタイプに分類されます。
治療方法は、骨折のタイプや年齢、全体の健康状態などによって決まります。
骨折は通常、強い外力が加わることで起こるため、皮膚、神経、血管、筋肉、さらには内臓にも損傷を伴うことがあります。
そのような場合、治療はより複雑で慎重な対応が必要となります。
小型犬の普及により、骨折・脱臼が増加
近年、日本で人気のある犬種として、1位トイ・プードル、2位チワワ、3位ミニチュア・ダックスフントが挙げられます。
これらの犬種はすべて体重が 5kg 以下の小型犬で、骨や関節が非常に弱いため、骨折や脱臼を引き起こしやすいです。
以前は交通事故による骨折が多かったのですが、現在では段差からジャンプして骨折したり、壁にぶつかって骨折したり、足元にいる小型犬を飼い主様が誤って踏んでしまうといったケースがよく見られます。猫の場合は、高いところからのジャンプによる骨折が多く報告されています。
症状と来院の目安
骨折や脱臼が起こると、ペットは怪我をした足を地面につけないようにしたり、触られると痛がるなどの行動を見せます。
しかし、ワンちゃんや猫ちゃんは「痛い」と言葉で訴えることができません。
そのため、飼い主様が気づかないことがあり、症状を放置してしまうケースも少なくありません。
気づかず放置すると、筋肉が硬直し、骨の修復に時間がかかることがあります。最悪の場合、骨が元に戻らないこともあるため、異変を感じた際には早めに当院にご相談ください。
骨折治療のアプローチと手術方法
骨折した骨を元の位置に戻し、プレートやピンを使用して固定する外科手術が一般的な治療法です。
固定することによって、骨が正常に癒合することを促進し、ペットが元の健康状態に回復することを目指します。
手術後は経過観察やリハビリを行い、しっかりと骨が癒合するように当院で丁寧なケアを提供します。
結石手術
結石は犬や猫にも発生します
結石は、尿路や胆管などに石ができることで、痛みや尿が出にくいといった症状を引き起こします。
特に尿路結石の場合、頻繁にトイレに行く、血尿が出る、痛がるなどの症状が見られます。
放置すると症状が悪化し、ペットの健康に重大な影響を及ぼすことがあります。
結石の治療と手術の流れ
小さな結石の場合、特別な食事療法や薬を使って治療できることがありますが、大きな結石や尿路の詰まりがある場合には、手術が必要です。
当院では、エコーやレントゲンを使用して結石の位置やサイズを正確に把握し、最適な手術を行います。
結石を取り除くことで、ペットの痛みを和らげ、健康を取り戻します。
手術をお考えの飼い主様へ
手術を検討される飼い主様にとって、手術に対する不安は少なくないかと思います。
当院では、手術前にしっかりとした説明を行い、飼い主様のご意向に沿った治療プランを提案しています。
また、術後の経過観察やリハビリもサポートし、ペットが早期に回復できるよう努めます。どのような状況でも、飼い主様とペットに寄り添い、最善のケアを提供することをお約束いたします。