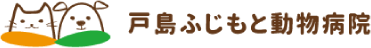様々な病気の
予防にもつながります
去勢や避妊手術は、動物の健康を守るために非常に重要な手術です。
この手術を受けることで、多くの病気を予防することができます。
去勢手術について
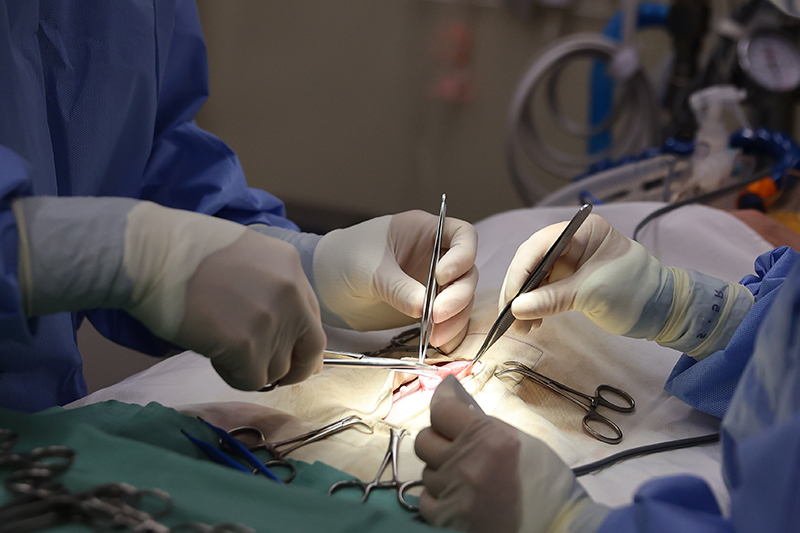
去勢手術とは
去勢手術は、オスの動物に対して行われる手術で、精巣を摘出することで繁殖を防ぎ、病気のリスクを減らすことが目的です。
去勢手術で予防できる病気
前立腺肥大
前立腺が大きくなり、排尿困難や感染症を引き起こすリスクを軽減します。
前立腺炎
前立腺の炎症を予防することで、痛みや不快感を防ぎます。
精巣腫瘍
精巣のがんや腫瘍のリスクをなくします。
会陰ヘルニア
肛門の周囲の組織が弱くなることを防ぎます。
肛門周囲腺腫
肛門周囲にできる腫瘍の発生を抑えます。
避妊手術について

避妊手術とは
避妊手術は、メスの動物に対して行われる手術で、卵巣や子宮を摘出することで繁殖を防ぐと同時に、将来の病気のリスクを減らします。
避妊手術で予防できる病気
乳腺腫瘍
特に早期に避妊手術を行うことで、乳腺腫瘍の発生リスクを大幅に減少させます。
子宮蓄膿症
子宮内に膿が溜まる病気を防ぎ、命に関わるリスクを回避できます。
子宮内膜炎
子宮の内膜の炎症を防ぎ、将来の健康問題を未然に防ぎます。
卵巣腫瘍
雌の犬や猫に発生する腫瘍で、悪性化や他の臓器へ転移を予防できます。
去勢・避妊手術の
メリット・デメリット
去勢手術のメリット
望まない繁殖が防げる
去勢手術は、オスの動物が計画外に繁殖するリスクを防ぎます。
もし望まない繁殖が起こった場合、飼い主様にはその後の世話や新たな責任が生じます。
去勢手術によって、飼い主様の負担を軽減することが可能です。
尿スプレー・マーキングの減少
オス猫やオス犬に見られるマーキング行動、特に家の中での尿スプレーが劇的に減少します。
これは、性ホルモンの減少によって縄張りを主張する必要性が低くなるためです。
攻撃行動・ケンカの減少
繁殖行動を理由とした攻撃的な行動や、他のオスとのケンカが少なくなります。
結果として、ストレスの軽減や家の中でのトラブルが減り、飼い主様にとっても飼いやすくなります。
脱走行動の減少
特に繁殖期には、外に出てメスを探そうとする脱走行動が見られることがありますが、去勢を行うことでそのリスクが軽減します。
動物の安全を守るためにも、脱走の減少は大きなメリットです。
ストレスの軽減
性ホルモンの影響で繁殖欲が強くなり、常に興奮状態になることが減ります。
去勢後は性欲が抑えられ、動物が穏やかに過ごせるようになることが多いです。
去勢手術のデメリット
手術のリスク
去勢手術には全身麻酔が必要となり、まれに麻酔に対するリスクがあります。
健康な動物であれば大きな問題はありませんが、麻酔自体がリスク要因となることがあります。
体重増加の可能性
ホルモンバランスの変化により、食欲が増し、運動量が減ることから太りやすくなることがあります。
飼い主様が体重・食事・運動管理を行うことが重要です。
性格の変化
性ホルモンの影響が減ることで、去勢後に動物が穏やかになる一方で、活発さが少し減ることがあります。
飼い主様によっては、以前の活動的な性格が恋しく感じるかもしれません。
避妊手術のメリット
望まない妊娠を防ぐ
避妊手術は、飼い主様が意図しない妊娠を防ぎます。
発情期には、意図せず交尾し妊娠してしまうことがあり、その結果、子犬や子猫の世話、里親探し、動物病院でのケアなど、飼い主様に大きな負担がかかります。
避妊手術を行うことで、これらの負担を事前に防ぐことができます。
病気のリスクを減らす
避妊手術により、乳腺腫瘍や子宮蓄膿症、子宮内膜炎といったメス特有の病気の発症リスクが大幅に減少します。
特に乳腺腫瘍は、早期の避妊手術を行うことで予防効果が高まります。
性周期の行動を抑える
発情期になると、メスの動物は特有の鳴き声や行動(脱走しようとするなど)を見せることがありますが、避妊手術を行うことでこれらの行動が減少します。
発情期に伴うストレスが軽減され、日常生活が穏やかになります。
ストレス軽減
避妊手術を行うことで、発情期によるホルモンの変動がなくなり、動物がより安定した生活を送れるようになります。
これにより、性ホルモンに伴う精神的ストレスも軽減されます。
避妊手術のデメリット
手術のリスク
去勢手術と同様に、全身麻酔を使用するため、麻酔に対するリスクが伴います。
また、避妊手術は去勢手術に比べてやや複雑な手術であるため、若干のリスクが増えることもあります。
体重増加の可能性
避妊後はホルモンバランスが変化し、体重が増えやすくなる傾向があります。
食事の管理や適切な運動を行い、肥満防止に努めることが重要です。
性格の変化
性ホルモンの影響が減ることで、活動性が少し低下することがあります。
一般的には性格が穏やかになることが多いですが、動物によっては元気さが減少することもあります。
尿失禁
去勢手術後、一部の雌犬ではホルモンバランスの変化により尿失禁が起こることがあります。
特に大型犬で発生しやすい傾向がありますが、適切な治療や管理で改善が可能です。
去勢・避妊手術を
受けるタイミング
子犬や子猫の場合
去勢・避妊手術は、生後6ヶ月頃から可能です。
メスの場合は、初回の発情が生後8ヶ月目以降に起こることが多いため、それ以前に手術を行うことをおすすめしています。
初回発情前に手術をすることで、乳がんの発生率を 90% 以上抑えることができます。
成犬や成猫の場合
成犬や成猫でも、去勢・避妊手術は可能です。
ただし、メスの場合は発情期に手術を行うと血管が発達しており、出血のリスクが高くなります。
現在発情中の場合は、2ヶ月程度の間隔を空けてからの手術をおすすめします。
繁殖を予定していない場合や発情が不規則な子には、早めに手術を行うことが理想的です。
去勢・避妊手術の流れ
ご予約
去勢・避妊手術は予約制です。
必ず事前にご予約ください。
事前診察
安全な手術を行うために、事前に身体検査や血液検査などを実施し、体調を確認させていただきます。
手術前日
全身麻酔を行うため、手術前日の20時以降は絶食をお願いしています。
当日朝は飲水のみ可能です。
手術当日
ご予約の時間にご来院ください。
ペットの体調を確認し、問題がなければお預かりいたします。
手術
全身麻酔下で去勢・避妊手術を行います。
手術中は生体モニターで心電図、心拍数、脈拍、血圧、呼吸、体温、酸素飽和度などを常時監視し、万全の体制で安全な手術を心がけます。
手術時間は通常30分から1時間程度です。
お迎え
手術は基本的に日帰りとなります。
お迎えの時間は、当院からお知らせいたしますので、その時間にお越しください。
手術後の注意点
おうちに帰ってからは、ペットに激しい運動をさせないようにしてください。
また、術後は傷を舐めないよう、エリザベスカラーが必要です。
お風呂は、抜糸が終わるまで控えてください。
もしご自宅で異変を感じた場合は、すぐに当院までご連絡ください。
抜糸
去勢・避妊手術後、約10日後に抜糸を行います。
当院の特徴
徹底したリスク管理

手術前には、血液検査に加えて年齢に応じたレントゲン、エコー、心電図検査などを実施します。
全身状態を評価し、内臓や心肺機能に問題がないか、手術のリスクを慎重に確認した上で、手術が安全であると判断された場合にのみ手術を行います。
鎮静剤・鎮痛剤による痛みの管理

術前から鎮静剤や鎮痛剤を使用することで、手術中や術後の痛みやストレスを軽減し、動物への負担を最小限に抑えます。
生体モニターによる術中監視

手術中は静脈確保や気管挿管を行い、生体モニターで心電図、呼吸、血圧、麻酔濃度などを常時監視します。
これにより、体調の急変にもすぐに対応できる体制を整えて、安全な手術を行います。