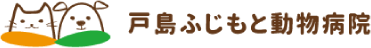ワンちゃん・猫ちゃんに
こんな症状はありませんか?
- 口臭が気になる
- 口から出血している
- 食べる時に嫌がる
- よだれが多い
- 鼻水が出ている
- 歯茎が腫れている
- 食事を食べづらそうにしている
- 歯に歯石がたくさん付いている
- 硬いものを噛みにくそうにしている
- 歯がグラグラしている
- 頬が腫れている
- くしゃみや鼻水が多いなど
これらの症状が見られる場合、歯周病の可能性があるため、早めにご相談ください。
犬猫の歯周病
歯周病とは

歯周病は、歯垢(プラーク)が原因で歯の周りに炎症が起こる病気です。
進行すると口臭が強くなり、痛みから食欲が低下したり、歯が抜けることもあります。さらに、下顎の骨が折れたり、心臓や肝臓などに病気を引き起こす可能性もあります。
多くの犬猫が歯周病に

犬や猫も人間と同様に歯周病にかかります。
3歳以上の犬や猫の約8割が歯周病を患っていると言われており、デンタルケアの重要性がますます注目されています。
歯周病は初期には症状が出にくいため、気づいた時には進行していることが多いです。
少しでも気になることがあれば、早めに当院へご相談ください。
歯周病が進行すると現れる症状
くしゃみ・鼻水・鼻血など
犬は口と鼻の間を隔てる骨が薄いため、歯周病が進行してその骨が溶けると、鼻腔に繋がってくしゃみや鼻水、鼻血といった症状が現れます。
これらの症状は歯周病のサインかもしれませんので、早めの診察をおすすめします。
皮膚に穴が開く
歯周病が悪化して炎症が歯の根まで広がると、周りの骨が溶けて「瘻管(ろうかん)」と呼ばれるトンネルが皮膚に形成されることがあります。
この瘻管からは血膿が出ることがあり、感染が進行している状態です。
小型犬の下顎骨折
小型犬は歯が大きく、下顎の骨の厚さが比較的薄いため、歯周病が進行して骨が溶けると、硬いものを噛んだり、外部からの軽い衝撃でも下顎が骨折してしまうことがあります。
特に進行した歯周病を放置しておくと、日常の中で骨折のリスクが高まります。
心臓や肝臓への影響
歯周病は口腔内だけでなく、全身の健康にも影響を与える病気です。
歯周ポケットの血管を通じて歯周病菌や炎症性物質が全身に運ばれると、心臓病や肝臓病のリスクが高まります。
さらに、腎臓にも影響を及ぼし、糸球体腎炎などの病気を引き起こす可能性もあるため、全身的な健康管理が重要です。
当院で行うデンタルケア
口の健康チェック

当院では、犬や猫の歯周病予防のため、定期的に口の健康チェックを行っています。
歯垢や歯石の付着具合、歯茎の状態を詳しく確認し、歯周病が進行していないかを確認します。
もし、初期の歯周病が見られる場合は、家庭でのケア方法をアドバイスし、進行している場合には歯科処置をご案内いたします。
ケア方法をアドバイス
デンタルケアの大切さを理解している飼い主様でも、「歯磨きを嫌がる」「どのようにケアをしたらいいかわからない」といった悩みをお持ちの方は多いでしょう。
当院では、その子に合ったケア方法を丁寧にアドバイスいたします。
また、歯磨きが難しい場合には、デンタルガムやサプリメントなどを提案し、少しでも口腔内が清潔に保たれるようお手伝いします。
歯周病の治療

歯周病が進行している場合、歯垢・歯石を取り除く「スケーリング」を行います。
スケーラーという専用の器具を使って、歯の表面や歯周ポケット内に付着した歯垢・歯石をきれいに除去します。
ただし、この処置には全身麻酔が必要です。
麻酔をかける理由は、麻酔なしでは歯周ポケットの深い部分まで確実に汚れを取り除くことが難しいためです。
軽度の歯周病であれば、視診のみで判断できますが、進行している場合には全身麻酔下でレントゲン検査を行い、歯やあごの骨(歯槽骨)の状態を確認します。
歯周病が重度に進行している場合には、抜歯が必要になることもあります。
そのため、スケーリングを行う前に、麻酔下での処置が可能かどうか、血液検査を含めた事前の健康状態の確認を行います。
ご家庭でのブラッシング方法
ワンちゃん・猫ちゃんの歯周病を予防するためには、ご家庭での歯磨きが非常に重要です。
しかし、多くのペットが口に歯ブラシを入れられることを嫌がるため、当院では飼い主様に適切なケア方法をアドバイスしています。
お口の周りに慣れさせる

まずは、ワンちゃんや猫ちゃんにお口の周りを触られることに慣れてもらいます。
これにより、徐々に口周りへの抵抗がなくなります。
唇をめくって歯や歯茎に触れる
次に、ワンちゃんや猫ちゃんの唇をめくり、歯や歯茎に軽く触れてみましょう。
もし嫌がるようなら、触った後に好きなおやつを与えて、少しずつ慣れさせることが大切です。
歯ブラシに慣れさせる
歯や歯茎に触れられることに慣れたら、歯ブラシを口元に当ててみましょう。
口にブラシが当たることに慣れるまで、焦らず少しずつ進めましょう。
ブラッシングを始める
抵抗がなくなったら、いよいよブラッシングを始めましょう。
最初は優しく、短時間で構いません。
少しずつ慣れてきたら、徐々にブラッシング時間を延ばしていきましょう。